【2023年】入梅の日にちいつ?意味や梅雨入りの違いを解説

日本において季節の移り変わりを把握するために定められた暦日を『雑節』と言いますが、『入梅』は雑節の一つです。
今回は入梅の日にちや入梅の意味や役割について詳しく解説していきます。
【2023年】小暑の日にちはいつ?意味や由来について

日本において暑くなってくる時期に“小暑”という季節がやってきます。
小暑は年によって日にちが異なり、少しややこしい一面があります。
そこで今回は2023年の小暑の日にちに加えて、意味・由来について詳しく解説していきます。
【2023年】(残暑)暑中見舞いの返事の時期・期間はいつまで?文章の例文もご紹介
 暑中見舞いにの返事に関する記事です。
暑中見舞いにの返事に関する記事です。
「いつまでに出せばいのか?」「暑中見舞いと残暑見舞いどちらで出せばいいのか?」 そして、「文章はどういう風に書けばいいのか?」
などについて説明しています。
是非参考にしてもらえればなと思います。
【2023年】雛祭り(桃の節句)の由来・意味・日にち

ひな祭り(桃の節句)の由来や意味、日にちについての記事です。
ひな祭りは、地域によって日にちが違うことがあり、そのことについて解説します。
また、ひな祭りの由来、そもそも桃の節句とは何なのか?ということを説明します。
【2023年】雛祭り(桃の節句)の雛人形を飾る時期はいつから?

節分が終わってちょうど1ヶ月経ったら今度はひな祭り(桃の節句)があります。
ひな祭りにには雛人形を飾るのが一般的ですが、いつごろ飾ればいいのか悩む人は多いのではないでしょうか。
今回、雛人形を飾るのに良いとされる日について解説していくので、いつ飾るべきか悩んでいる人は是非参考にして下さい。
【2023年】春・秋のお彼岸はいつ?彼岸入り~明けの期間

毎年春・秋の2回お彼岸はありますが、年によって若干日にちがズレるため、ややこしいと感じる人も多いと思います。
お彼岸の期間がどのように定められているのか、なぜ年によってズレが生じるのか。
2023年の春のお彼岸・秋のお彼岸の期間と合わせて解説していきます。
【2023年】春分の日にちはいつ?意味や由来・日照時間について

春分の日は昼夜の時間がほぼ等しく、日照時間が約12時間になるという特徴的な日ですが、年によって日付が変わるという厄介な点があります。
春分の日に関して、なぜ昼夜の時間が等しくなるのか、春分の日にちはどのように定められているのか、気になる人も多いのではないでしょうか。
今回は2023年の春分の日付に加え、これらの疑問について徹底的に解説していきます。
2023年は卯年!干支の「癸卯」の特徴や意味について解説

2023年の干支は十二支で言うところの「卯年(うどし)」ですが、正確に干支を表すと「癸卯(みずのと・う)」です。
干支は実生活において年以外にも「丑三つ時」や「土用丑の日」などの時間や暦などを表すこともありますが、一方で運勢や性格、相性などの占いなどにも使われます。
今回は2023年の干支「癸卯」における特徴について解説していきます。
立春とは?2024年の日にちはいつ?
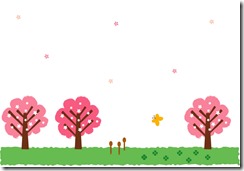
立春の概要・日にちについてまとめてみました。
季節感を大事にしてきた私たち日本人はいつのまにか何事にも利便性に目が行くようになり、このような季節に関して関心が希薄になってきたように思います。
是非これを機に日本人ならではの感覚を思い直していきましょう。
暑中見舞いはがきのネット注文の手順と比較(料金・日数)

暑中見舞いのはがきの作成方法は主に4つありますが、今回はオンラインサービス(ネット注文)を活用するメリット・デメリットや手順について詳しく解説していきます。
それぞれの方法にはメリット・デメリットがありますが、ネット注文は以下のような人におすすめの方法です。
- 家にカラープリンターがない
- 見栄えの良い仕上がりにしたい
- お金がかかってもできるだけ手間はかけたくない
- 大人数に出す必要がある
【2023年】敬老の日の日にちはいつ?由来や意味もご紹介

敬老の日に関して、
「2023年の敬老の日の日にちはいつなのか?」
「敬老の日の制定の経緯や由来はどんなものなのか?」
「敬老の日と老人の日は何が違うのか」
など解説していきます。
是非参考にして下さい。
2022年は寅年!干支の「壬寅」の特徴や意味について解説

2022年の干支は十二支で言うところの「寅年(とらどし)」、ウシに当たるわけですが、正確に干支を表すと「壬寅(みずのえ・とら)」です。
干支は実生活において年以外にも「丑三つ時」や「土用丑の日」などの時間や暦などを表すこともありますが、一方で運勢や性格、相性などの占いなどにも使われます。
今回は2022年の干支「壬寅」における特徴について解説していきます。
2021年は丑年!干支の「辛丑」の特徴や意味について解説

2021年の干支は十二支で言うところの「丑年(うしどし)」、ウシに当たるわけですが、正確に干支を表すと「辛丑(かのと・うし)」です。
干支は実生活において年以外にも「丑三つ時」や「土用丑の日」などの時間や暦などを表すこともありますが、一方で運勢や性格、相性などの占いなどにも使われます。
今回は2021年の干支「辛丑」における特徴について解説していきます。
【丑(うし)】2021年の年賀状の無料イラスト・テンプレートまとめ
2021年の年賀状のイラスト素材・テンプレート素材についてまとめました。
2021年は丑(うし)年なのでウシのイラスト、またその他にも正月に関するイラストの七福神、正月飾り、富士山のイラストなど様々な種類のものが揃っています。
また、可愛いもの、かっこいいもの、おしゃれなもの、ユニークなものなど色んな素材があるので、是非参考にしてみてください。
2020年の梅雨入り・梅雨明けはいつ?過去のデータと日にち予想
梅雨入りや梅雨明けは年によって日にちが大きく前後します。
時期が近づかないことには詳細な予測は立てられませんが、過去のデータから大体の目安をつけることができます。
今回は地域ごとの過去のデータを見やすくまとめ、さらに2020年の梅雨入り・梅雨明けの目安を紹介していくので是非参考にして下さい。
半夏生とは?2020年の半夏生の日にちはいつ?

日本の季節に“半夏生(はんげしょう)”というものがあり、この日には地域によって特有の食べ物を食べる風習があったりします。
ただし、この半夏生は年によって日にちがずれたりもするため少しややこしい日でもあります。
今回は今年の半夏生の日付に加えて、半夏生の意味や日付の定まり方、各地の風習について詳しく説明していきます。
2020年10月はブルームーン!日にち・定義について解説

ブルームーンはいろんな定義がありますが、現在一般的なのは「ひと月に2回満月になること」を指します。
満月の周期は約29.5日。
現在の暦は2月以外はひと月30日、または31日とこれよりもわずかに長いため、月のはじめと終わりに満月になることがあるのです。
今回、ブルームーンの日にちや詳細について解説していきます。
うるう年とはいつなのか?一覧と計算方法&仕組みを図解
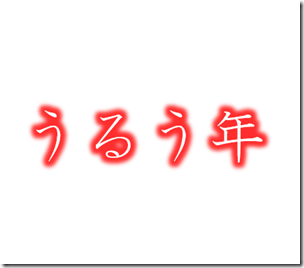
閏年(うるう年)とは、2月29日が存在する年を指し、それは約4年に一度巡ってきます。
つまり、通常1年は365日であるのに対し、うるう年は366日になるということですね。
今回、うるう年はいつなのか、その計算方法や一覧、仕組みをご紹介します。
ちなみに、次のうるう年は2028年。
そして次回以降は2032年、2036年、2040年・・・となります。
2020年(令和2年)国民の祝日一覧カレンダー
2020年は以下の理由により、例年とは祝日の日にちが異なるものがあります。
- 昨年の皇位継承に伴い、天皇誕生日が変更
- 12月23日⇒2月23日
- 東京オリンピック・パラリンピック開催の影響で日にち変更
- 海の日:7月第3月曜日⇒7月23日(開会式前日)
- 体育の日(今年から「スポーツの日」):10月第2月曜日⇒7月24日(開会式)
- 山の日:8月11日⇒8月10日(閉会式)
では具体的にカレンダーとともに、2020年の祝日を見ていきましょう。
